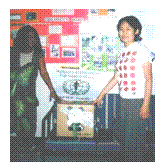当会にご協力いただいている、大波奈津美さんが2004年1月12日から同年17日までを ジャマイカで過ごされ、当会の支援する孤児院を訪問し、そのレポートをお送りいただきました ので、ご紹介させていただきます。
以下、大波奈津美さんからいただいたレポート
私が訪れた孤児院二カ所について、感じたことをお伝えしようと思います。
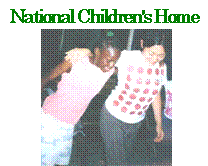
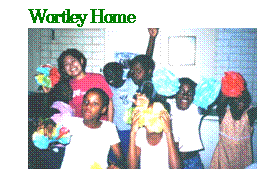 この孤児院には、8〜15歳の女の子13人が生活しています。キリスト教の精神に基づいて運営されているので、子どもたちも落ち着いた生活を送っていました(もちろん、元気いっぱいですが)。ジャマイカに着いて初めて訪れる孤児院だったので、折り紙を上手く教えられるか、英語が通じるかどうか不安と緊張でいっぱいでした。そんな私を、スーパーバイザーのマーティンさんが丁寧な英語と笑顔で迎えてくれました。
この孤児院には、8〜15歳の女の子13人が生活しています。キリスト教の精神に基づいて運営されているので、子どもたちも落ち着いた生活を送っていました(もちろん、元気いっぱいですが)。ジャマイカに着いて初めて訪れる孤児院だったので、折り紙を上手く教えられるか、英語が通じるかどうか不安と緊張でいっぱいでした。そんな私を、スーパーバイザーのマーティンさんが丁寧な英語と笑顔で迎えてくれました。
初めに自己紹介。そして、次に折り紙と花紙でお花作りを子どもたちに教えました。初めは、私の緊張が伝わったのか、お互いぎこちなかったです。でも、徐々に慣れてきて、子どもたちも「ミス。」と言って、質問してくれました。一度覚えてしまうと、みんな熱中してお花を作っていました。日本語にも興味を示してくれて嬉しかったな。
今度は、反対に私にジャマイカの国の花、英雄、お金について教えてくれたり、国歌を歌ってくれたりしました。私も、日本の国歌を歌いましたが、緊張して声が裏返る裏返る。練習しとけば良かった。。。その後、彼女たちは私にダンスを教えてくれました。とってもとっても楽しかったです。
私は、東京でアフリカンダンスを習っているのですが、ジャマイカのダンスも似ているところがあり、あの腰の動きはいくら練習しても習得出来ません!もっともっと、教えてもらいたかったです。お庭には、フルーツの木がたくさんあり、プラムを外に行って取ってきてくれました。とっても嬉しかったし、おいしかった。何よりも、彼女たちの心が嬉しい。
ずっと一緒にいるうちに、やっぱり自分がいたいのは、関わりたいのはこういう空間だなあと思いました。(私は、学生の時から国際協力に少しずつ足をつっこんできたのですが、今は社会にでて修行中なのです)。彼女たちは、きっと愛情をめいっぱい受けていないだろうに、人一倍優しさがあるように感じました。それに、お疲れOLの私に、たくさんの元気をくれるんです。すぐ近くに親のいない環境。自分は体験したことがないので、どう言って良いか分からないけれど、何か世の中おかしい。でも、この私がおかしいと感じる世の中にきっと、どこかで自分もつながっていると思うし、大きな責任を感じてきました。ずっと、一緒にいたい、この出会い、つながりを大切にしたいと思いました。
ご飯も一緒に頂きました。なんだか、とっても申し訳なかった。でも、同じものを一緒に食べれることが嬉しかったです。この日の晩ご飯は、1きれのピザとコーラ。みんな一緒。私が、8歳、ましてや15歳の時どれほどのご飯を食べていただろう。高校生の時など、朝ごはん、早弁、お昼、おやつ、夕食。。。どうして、こうも違うのか。
帰りには、自分たちは食べていないのにバナナをお土産にくれた。この子たちは分けるということを知っている。いくら私がお金を持っていようとも。世界の資源、富を誰かの所有物のように奪い合い、戦争を好む人々に学んでもらいたいです。
Wortley Home とは違う雰囲気を入った瞬間から感じました。平松さんからお預かりした支援物資を持っていったので、棒を持った女の子が、「食べ物?お金持ってる?」と聞いてきました。この時、緊張を感じると同時に、彼女にこう言わしめているのは何なのか。。。と思うのでした。この孤児院には、身体的に障害を持った子供たちも一緒に生活していて、約80人の子どもたちがいます。
スーパーバイザーの方にご挨拶をした後、美術の先生をしている方が15人くらいの子どもたちとエクササイズをしているのを見学しました。この孤児院の子どもたちは、先生がお話をしていても一人としてじっとしていることが出来ません。
スタッフの方は何度も何度も注意していました。また、彼らには一つのことをするのに、多くの時間を必要とします。その光景をみて、何度も涙腺がゆるみました
少し前に日本で問題になった学級崩壊を思い出しました。ジャマイカ、日本、どちらの子どもたちも「何か」が足りないのだと思いました。先生が、子どもたちに好きなものを聞きました。彼らの多くは、家族について触れます。家族と一緒に過ごしたいの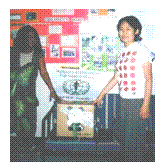 です。彼らには、家族というものがどういうものか分かっているのです。
です。彼らには、家族というものがどういうものか分かっているのです。
私は、当たり前のように家族が周りにいました。がしかし、私も大学から東京に出て、働き一人暮らしをしていると、家族の大切さがとても良く分かります。
また、先生が私と一緒に行ってくれたハイヤシンスさんに、この仕事はとてもストレスフルだと言っていました。どうして、ジャマイカのこんなゆったりとした生活でストレスが溜まるのだろうと思いましたが、子どもたちとの関わりの中で、ご苦労されているのだろうと思いました。
一人の女の子(おそらく12歳くらい。)が、時々赤ん坊のように指をくわえていました。また、HOMEに着いてすぐに、5歳くらいの男の子が手をつないで来ました。彼は、言葉を発することが出来ないけれど、とても人なつこい。でも、一度も笑うことはありませんでした。7歳くらいの女の子が私の隣に来て、手を離さず、ずっとダンスをするまねをしていて、膝の上に顔を持ってきたり抱きついてきたり、「髪の毛直してあげる。」と私の髪に触れてきたり。でも、彼女は、私がちょっとした質問をしてもそれに答えてくれることはありませんでした。この女の子と、さっきの男の子が私の手の取り合いを始めました。一本ずつ手を渡しましたが、私がこの子たちの母親になれたら。。と無責任なことを思ってしまいました。
子どもたちが食事を終えた後、歌やダンスを披露してくれました。とても楽しかったし、みんなの前で自分を表現し、楽しそうでした。ダンスを教えてもらったり、一緒に写真を撮ったりしていると、女の子二人が椅子を持ち上げてのケンカを始めました。彼女たちは攻撃的です。どうして、彼女たちがこうなってしまうのだろう。。数人の子どもたちが、私を外の階段のところに避難させてくれました。
みんな、ネガティブな意味でパワフルだったので、少々不安でしたが、平松さんが何度も来ているから日本が好きなようでした。一人の女の子が「私を日本に連れてってくれる?」と聞いてきました。「もちろん。」と答えると、「いつ?」と言われ、少しとまどってしまいましたが、いつか日本を紹介したいと強く思いました。
ここの子どもたちは攻撃的な感じでしたが、やっぱり子ども。元気で素直。たくさんのパワーをくれました。どちらの孤児院とも一度しか、訪問できなかったのが残念でした。もっともっと、こどもたちと遊びたかったです。
また、子どもたちのふとした表情から寂しさを 感じないことはありませんでした。孤児院に来るのには、レイプによって生まれた子ども、家庭内暴力、おきざり、子どもをみれないために週末だけ家族と過ごす等の理由があげられるそうです。ジャマイカでモラルについて教えているサーモンさんが、私に教えてくれました。まず、教育をピラミッドで考えると、まず土台には道徳、その上に倫理、そして頂点に知識がくるのだと。でも、今はそれが逆転してしまっていると。日本でも同じ事が言えるのではないかと思いました。
私は、親になったことはありませんが、電車で騒いでいる子どもを他人のように見ている親を見ても、人として大切なものを教えることを忘れている、放棄しているように思えます。帰りの飛行機の中で、泣きわめく子どもがいました。(もちろん、子どもは泣くものですが、尋常ではないのです。)
与えられるものを与えられすぎた子ども。愛情が不足しているけれど、私に愛情を注いでくれ、分け与えることを知っている子ども。この旅では、両極の子どもの姿を見、感じた気がしました。ジャマイカの自然、人、食べ物、ゆっくりした空気は、たくさんのパワー、元気を私に与えてくれました。とってもここちよかったです。帰路、何度戻ろうと思ったことか。
この出会いを大切に、みんなとつながっていこうと思います。
そして、出来ることから始めていこうと思います。
平松さんに感謝、両親・家族・友人に感謝、サーモンさん・ハイヤシンスさんに感謝、ジャマイカに感謝、すべてに感謝!! 2004年 1月 大波 奈津美
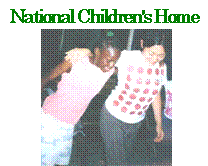
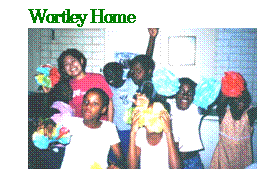 この孤児院には、8〜15歳の女の子13人が生活しています。キリスト教の精神に基づいて運営されているので、子どもたちも落ち着いた生活を送っていました(もちろん、元気いっぱいですが)。ジャマイカに着いて初めて訪れる孤児院だったので、折り紙を上手く教えられるか、英語が通じるかどうか不安と緊張でいっぱいでした。そんな私を、スーパーバイザーのマーティンさんが丁寧な英語と笑顔で迎えてくれました。
この孤児院には、8〜15歳の女の子13人が生活しています。キリスト教の精神に基づいて運営されているので、子どもたちも落ち着いた生活を送っていました(もちろん、元気いっぱいですが)。ジャマイカに着いて初めて訪れる孤児院だったので、折り紙を上手く教えられるか、英語が通じるかどうか不安と緊張でいっぱいでした。そんな私を、スーパーバイザーのマーティンさんが丁寧な英語と笑顔で迎えてくれました。